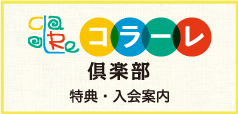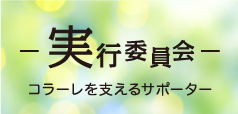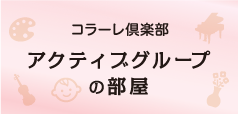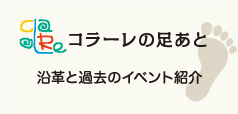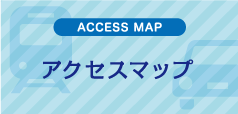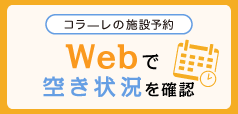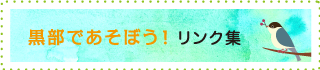ラレコ山への道 小野木豊昭 古典空間への誘い
コラーレ倶楽部
アクティブグループの部屋
COLARE TIMES
【其の伍拾伍】ベトナムの三味線……アジアはひとつ!
2009年6月

3月2日、ハノイにある歴史的なオペラハウスでの公演。両国の三味線を比較紹介する中井智弥。
今年は「日メコン交流年2009」。現在もメコン川流域の5カ国とさまざまな分野での交流が行われています。1月から3月にかけても、津軽三味線ユニット「あんみ通」や二十五絃箏の中井智弥と薩摩琵琶・尺八の長須与佳が各国でコンサートやワークショップを行い、日本文化の紹介に努めてきたことは、Vol.54「ホーチミン35℃」で報告させていただきました。
実はこの旅で私が密かに楽しみにしていたことがあります。それは「楽器探訪と収集」。会場の下見、現地スタッフとの打合せ、リハーサル、本番、取材等々、ほとんど余暇のない海外公演の仕事。スケジュールの隙間を見つけては、ピンポイントで地元の楽器屋さんを訪ねるのです。
楽器の分類ではスパイクリュート属といわれる種類にあたるそうですが、胴に棹が貫通していて抱えて弾く絃楽器を代表するのが日本の三味線です。その三味線のルーツが大陸に求められることはご存じの方も多いのではないかと思います。素材や奏法こそ違え、基本的な構造がここまで近い楽器を目の当たりにすると、何か暖かい親近感を超えた興奮と感動を覚えてしまうのです。
ベトナムには三味線に近い三絃の楽器が存在することを文献資料等で確認済みでした。そこで3月2日、ハノイのベトナム国家音楽院ホールにおける公演の際、間隙をぬって街に出ました。さすがに音楽大学の周辺、たくさんの楽器屋さんがあったのですが、一挺の三味線にも廻り合うことができませんでした。多少の落胆を込めて国家音楽院の民族音楽の先生にお話したところ、翌日オペラハウス公演の楽屋にわざわざ調達して持って来てくださったのです。ベトナム中部から北部にかけての農村等で踊りの伴奏等に使われるが、演奏者は非常に少ない楽器とのことでした。もし手に入ったら、地歌の三味線を弾く中井智弥が舞台上で紹介するという演出プランを胸に秘めていたので、日本の三味線を持参していました。楽器紹介のコーナーで両国の三味線を比較紹介した後、「やっぱりアジアはひとつなんですね!」と中井がコメントすると、600席満席の場内から万雷の拍手を頂き、大使からも「さっきのコメントはよかったよ」とお褒めの言葉を頂戴しました。
3月5日、南部のホーチミンでは、師範学校での公演も終わり、COLARE TIMES の原稿も上がって帰国に向けて出発直前に、市内の土産屋で三味線発見! しかも楽器として非常に質のよいもので、ハノイのものとは構造的に多少の相違がありました。もちろん購入しましたが、この三味線がどうのように演奏されているのか……楽しみな研究課題も土産として持ち帰りました。

中国の三味線(大三弦)(上)
一昨年モンゴル公演の際入手した三味線(中)
チベットの三味線(下)

ベトナムの三味線
ホーチミンで入手した三味線(上)
ハノイで入手した象嵌入りの三味線(下)
共に“カポタスト”が付いている。
(2009年06月 COLARE TIMES 掲載)